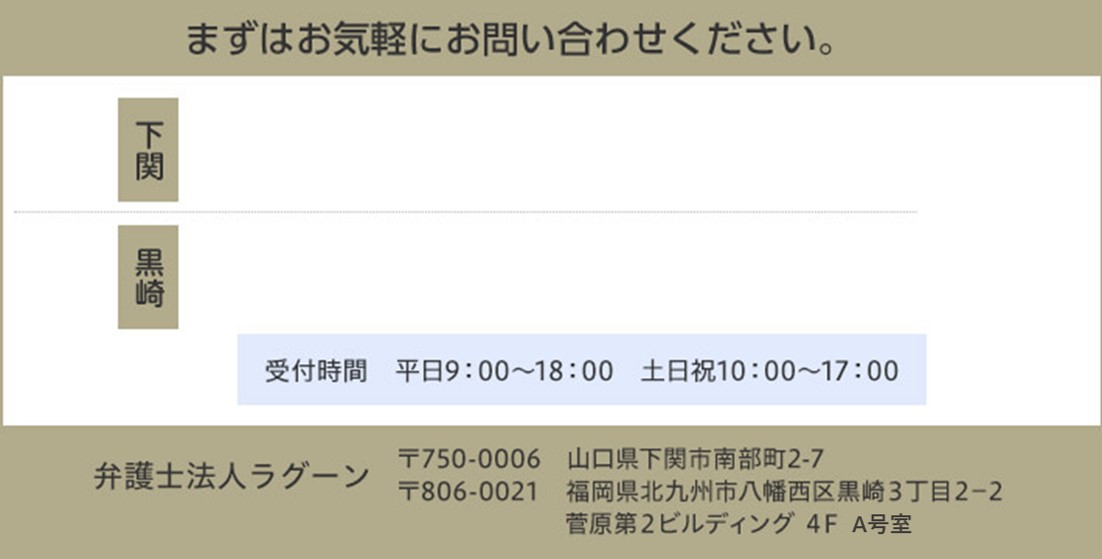「破産したら全てを失う・・・。」「底辺のような生活を強いられる・・・。」そんなに風に思われている方も少なくないでしょう。
しかし、結論からいうと、実は破産によって生活レベルが極端に下がることはあまりありません。ここでは、破産により破産者の生活がどのように変化するのかについて解説します。
1 破産制度の概要と破産によって失うもの
破産制度は、簡単にいってしまえば、破産者が所有する財産を、基本的に全て換価して(お金に換えて)、それを債権者に分配する代わりに、債務(≒借金)を免除する制度です。
ここで、「基本的に」というのがポイントです。破産法は、破産者の破産後の生活を考慮して①現金で99万円は保有していてもよい、②通常の家財など生活必需品は換価しなくてもよい、としています。つまり、生活必需品+現金99万円を超える部分だけが換価対象になるのです。
さらに、現金99万円と言いましたが、自由財産拡張制度というものがあり、実質的には「トータルで99万円」までは財産を保有してもよい運用になっています。
たとえば、現金10万円のほかに保険契約があり、当該保険契約を解除した場合に解約返戻金が15万円ほど入ってくるとします。この場合、この15万円も現金と同視して上記の「99万円の範囲内に収まっているか」を検討するのです。
破産を選択される方の多くが、生活必需品+99万円分の財産を超えて財産を持っていませんから、実務上、同時廃止といって破産手続の開始と同時に手続終了となることが多く、結局、破産者が何か財産を失うということはあまりないのです。
では、どういう場合が困るかというと、①自宅不動産を持っている場合、②自動車を持っている場合、です。
住宅ローン等を返済していない場合、自宅不動産に設定された抵当権を実行されてしまい自宅を失ってしまいます(これを回避する方法として「住宅資金特別条項付小規模個人再生」という手段があります。)。住宅ローンを完済している場合であっても、一般的に自宅不動産の換価価値が99万円以下であることは少なくないので、やはり、破産手続の中で換価されてしまうことが多いです。
また、自動車については、所有権留保がなされている場合(車検証をみて所有者欄が信販会社等になっている場合は所有権留保がなされている可能性が高いです。)、ローン未完済の状態で破産を選択すると引き揚げられてしまいます。自宅不動産と同様に、ローンを完済していても、換価価値の高い自動車の場合は、やはり、破産手続の中で換価されてしまいます。
逆に、以上に挙げた自宅不動産や自動車がない場合、何かを失って生活に支障をきたすということはほとんどありません。
2 破産後の生活
(1)良い面
債務が免責により無くなるので(厳密には「自然債務化」と言います。)、生活に余裕が生まれ、貯金が出来るようになることもあります。たとえば、①月手取25万円、②家賃・携帯代・公共料金などの借金以外の支払の月合計が15万円、③借金の支払が月15万円の方が破産した場合、③が消えますので、①-②=10万円で月10万円は貯金できるようになります。
「破産したら仕事を辞めないといけないので収入が無くなるのでは?」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、職業制限がかかる仕事は一定の職業(弁護士、生命保険募集人、証券取引外務員など)に限定されており、あまりこれらに該当することはありません。
上記1で解説したとおり、資産を処分しなくてはならなくなるケースは少ないので、結局、資産は何も失わないばかりか貯金すら出来るようになるということも結構あるのです。
(2)悪い面
破産すると信用情報登録されますので(いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているものです。)、クレジットカードでの買い物など信用取引が5~10年程度は出来なくなります。そのため、原則として、現金での生活になります。
現代において、若干不便ではありますが、生活に支障を生じるようなことではありません。
自宅不動産を失う場合は転居することになりますので、それに伴って慣れない生活がしばらく続きます。しかし、新しい住居での生活もいつかは慣れます。
自動車を失う場合、通勤手段等が公共交通機関に代わり、それが肉体的・精神的な負担となります。実務的には、破産手続中に貯めたお金で安い自動車を購入するか、親族の自動車を使わせてもらうことが多いです。
3 結論
以上をまとめると、「破産しても、換価価値の高い物を所有していない方は、借金が消えて生活が楽になるだけで生活に大きな悪影響は生じない。但し、クレジットカードの使用など信用取引はできなくなるので若干不便にはなる。」ということになります。
簡単に言ってしまえば、このようになりますが、上述した「同時廃止」ではなく管財事件といった類型の事件になって財産が換価されてしまったり、免責不許可事由の関係でそもそも破産を選択するのがリスキーな場合などもあり得るので、詳しくは弁護士に直接相談した方がよいです。